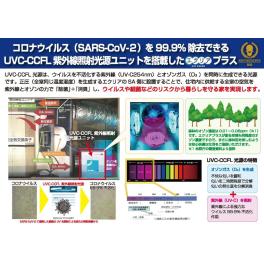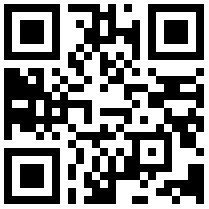現金は安全。でも、価値は守れない。
昨日書いた記事で、私は現金を持っていると、どんどん目減りするって書きました。その意味が分からないって言われましたので、今回は前回の記事の追記として、お金の仕組みについて簡単にお話いたします。
多分ですが、皆さんが思っている以上に深刻なことなので、ぜひ今回の記事で勉強をしてみてください。
では、以下は本分です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの財布や銀行口座にあるお金。
その額は変わらなくても、実は“中身”がどんどん減っているとしたら——
それはとても静かで、気づきにくい「損失」かもしれません。
今回は、「現金を持ち続けるリスク」について、わかりやすく解説していきます。
物価が上がれば、お金の価値は下がる
たとえば、1本100円だったペットボトルのお茶が、来年は110円になる。このように、物の価格が上がることを「インフレ(インフレーション)」といいます。
インフレが起こると、同じ金額でも買えるものが減ってしまう。
つまり、お金の「価値」が下がるということです。
とは言っても100万円と言う現金は、今100万円なら来年も100万円だし、再来年も100万円です。
日本が無くならない、もしくは円の相場をやめない限りは、100万円は100万円のままです。
だから、お金が減ると言われると違和感があるかと思います。
しかし、私が言いたいのは100万円の価値です。
この価値はどんどん変わるものなのです。
分かりやすい例をあげると、戦後の復興時1950年代では、かけそばの価格が10~20円だったと言う記録があります。
今のそばの価格は400円~600円程度でしたから、随分と安い金額で食べられたのです。
この1950年くらいの平均年収は10~15万円ほど、月収じゃなくて年収ですからね。
それくらいあれば普通に生活が出来たのです。
その頃の100万円といえば、超大金ですね。
年収の10倍もあるのですから、本当に大金です。
今で言うと、平均年収が450万円程度と言われているので、昔の100万円は今で言うと4500万円程度の価値だったと言えます。
その後戦後復興もあり、日本はどんどんインフレになり、今の物価に落ち着きました。
もし戦後の100万円を大事にして今でも持っている人がいたら、かなりの大損ですね^^;
4000万円以上も価値を損していることになります。
これが私が言っているお金の価値が下がるということなんです。
最近では、食品や日用品、光熱費などあらゆる物の価格が上昇傾向にあります。
ニュースでは「2%の物価上昇」と聞いても実感が湧きにくいかもしれませんが、 家庭の出費としては、5〜10%以上の体感を覚えている方も多いのではないでしょうか。
たとえば、いま100万円の現金を持っていたとして、 年間の物価上昇率が3%なら、1年後には実質97万円の価値に減っているということになります。
これは、目に見えない「目減り」です。
銀行に預けておけば安心? それ、本当?
「現金を家に置いておくのは怖いから、銀行に預けている」 「預金は安心で安全」 …たしかに、物理的な盗難や紛失のリスクは減ります。
でも、銀行に預けたからといって、お金が増えるわけではありません。
現在の日本の普通預金金利は、年0.001〜0.2%。 100万円を1年間預けても、利息はたったの10〜2000円程度です。
これでは、物価上昇のスピードにはまったく追いつけません。
むしろ、「銀行に預けていても実質的に損をしている」というのが現実なのです。
貯金することが、もはやリスクになっている時代
一昔前は、「貯金は美徳」でした。親から「しっかり貯金しなさい」と言われて育った方も多いでしょう。
でも、時代は変わりました。
貯金が増えても、それ以上に物価が上がる時代。
「使わない=守れる」ではなく、 「動かさない=減っていく」時代なのです。
もちろん、いきなり投資に手を出せというわけではありません。
でも、「ただ貯めているだけで安心」と思っているなら、 それはちょっと危ない考え方かもしれません。
日本人は「貯めすぎて」損をしている?
日本人は、世界的に見ても貯金好きな国民と言われています。例えば、2023年時点の家計金融資産を見ると、 日本ではおよそ50%以上が現預金で保有されているのに対し、 アメリカでは現金はわずか10%程度。
残りは株式や投資信託で運用されています。
この差は、「資産が増える力」にも直結します。
アメリカでは「貯める」より「増やす」意識が根づいているのです。
一方、日本では銀行にお金を預けておくだけで安心と考える人が多く、 結果として、インフレの波に飲まれ、知らぬ間に損をしている人が増えています。
実は昔は日本も貯金をしない国だった?!
こんな話をすると、日本は昔から倹約が美徳とされ、そういった社会になったなんて言う人もいます。
しかし、それは少し間違いと言えます。
日本は戦後くらいまでは、お金を持たない方が美徳とも言われていた国だったのです。
まあ、そんなに貯められるほどお金を持っていない人が多かったと言う事実もありますが・・・
それが戦時中や戦後、国の推奨で貯蓄することが美徳とされてきました。
特に郵便局を通した貯金が推奨されます。
その理由は様々ですが、国が推奨した最大の理由は『国民のお金を国が使えるようにするため』
昔は郵便局は国営であったため、郵便局に合ったお金は国が使うことが出来ます。
とは言っても、元は預けた人の物なので、無くしてしまうことは出来ませんが、国が貯金を推奨すれば、引き出すお金よりも、預けるお金の方が多くなるので、その分を国が使っても大きな問題にはならないと言った事実を上手に使ったのです。
戦時中は国にお金が無くなってしまったのですが、だからと言って税などで徴収すれば、パニックになってしまう。
だから表向きは、預けているとさせて、そのお金を使うことで、戦時中の財政難の足しにしたのです。
預ける方も、国が保証してくれると言われたら、その先の使い方まではあまり問わないですよね。
また、戦後も同じようにお金が無かった国が、国民のお金を利用するために貯金を推奨しました。
そのお金を国が吸い上げ、色々な資金として利用されてきたのです。
それがけしからんとして、1900年代末には問題視され、2000年初頭には郵政民営化として、その仕組みが使えなくなるまでは、50年以上に渡りその仕組みが使われてきたのです。
だから、日本人は昔から貯金が好きだったのではなく、戦中戦後にそのように誘導されてきたと言うのが正しい見方なのです。
どうすれば、お金の価値を守れるのか?
さて、余談が長くなりましたが、現金の価値が目減りすることを前提とするなら、 その対策としては「お金を動かす」ことが必要になります。主な選択肢としては以下のようなものがあります。
- 資産運用(投資信託、株式、iDeCoやNISAなど)
- 外貨分散(為替リスクはあるが、円安対策になる)
- 実物資産への転換(金、不動産など)
- 自分への投資(資格取得、スキルアップ)
いずれにせよ、「お金を動かす」という選択が、 これからの時代を賢く生きるためのキーワードになってきます。
“見えない損”に気づいた人から動いています
誰もが避けたいのは、大きな損失です。でも、もっと怖いのは「小さな損を、ずっと見逃していること」。
現金の目減りは静かで、目に見えません。
でも、確実に進行していて、気づいた時には手遅れになっていることもあります。
実際に、今の物価高もそうですし、海外などに行った際の物価の高さで感じることは出来ていると思います。
将来に備えてお金を貯めるのは大切。
でも、「どう守るか」まで考えることが、本当の意味での資産形成です。
まとめ:今こそ、お金と向き合うタイミング
・現金は安全だが、価値が下がっていく ・低金利とインフレの時代には「貯金=リスク」
・増やすだけでなく、守ることがこれからの資産管理
・動かさないことが最大の損になる可能性もある
今すぐ何かを始める必要はありません。
でも、「お金の持ち方を見直す」ことだけは、今からでもできます。
あなたのお金が、あなたの未来を守ってくれるように。
そのために、“ただ貯める”から一歩踏み出してみませんか?
その為の方法として、家を建てることがあります。
生涯の最大の買い物をなるべく安いうちに買っておく。
これも一つのリスク管理と言えそうです。
今回はここまで。
では、また!